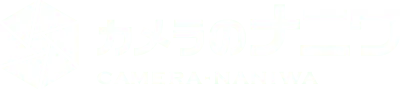こんにちは、カメラのナニワ鹿児島天文館店の米田です。
皆様は一眼レフやミラーレス一眼で写真を撮るとき、デジタルフィルターをお使いでしょうか?
トイカメラモードやミニチュアモードなど、写真にちょっとしたスパイスを加えることができるので、いつもとは一味違った風景を写し出すことができます。
フィルムカメラ全盛期のフィルターは、レンズの前面に装着して様々な効果を出していましたが、デジタルカメラに移行した今の時代では、カラーフィルターやクロスフィルターなどは電子的に再現ができるようになりました。
今でも「NDフィルター」や「PLフィルター」こそ使われていますが、その他特殊なレンズフィルターを使う方は少なくなってきているのではないでしょうか・・・
そこで、今回は様々なレンズフィルターをご紹介するとともに、実際にデジタルカメラに装着をして写真を撮ってきましたので、どのような効果があるのか、デジタルフィルターとはどのような違いが得られるのかをご紹介します!
1.保護フィルターとは
レンズフィルターは大まかに「保護フィルター」と「特殊効果フィルター」に分類できます。大多数の方は普段から保護フィルターを装着しておられるのではないかと思います。
保護フィルターはケンコーやマルミ、各社様々な製品が出ています。その役割はレンズの前玉を衝撃から保護するというものであり、レンズの写りそのものには可能な限り干渉しないよう透過率、反射率などが考慮され設計されています。
グレードも様々で、「ケンコー PRO1D」 のような安価ゆえ替えがききやすくコスパのいいものから、「マルミ EXUS」や「ケンコー Zeta」など写真の画質を上げるため更に性能が向上された高価なものまで、幅広く存在します。


2.特殊効果フィルターとは
特殊効果フィルターは保護フィルターと違って意図的にレンズの写りに変化をもたらすため設計されています。
それでは、今回どのような種類の特殊効果フィルターを使用するのかご紹介します。
①PLフィルター PLフィルター(偏光フィルター)のPLとは、Polarized Light(偏光) の略称です。2枚のガラスで偏光効果のある膜を挟む構造になっています。前側のガラスは枠ごと360度回転するようになっており、これを回転させて反射などによる偏光を遮断出来ます。
PLフィルター(偏光フィルター)のPLとは、Polarized Light(偏光) の略称です。2枚のガラスで偏光効果のある膜を挟む構造になっています。前側のガラスは枠ごと360度回転するようになっており、これを回転させて反射などによる偏光を遮断出来ます。
水面やガラス面などの反射光、物体のテカリ、空気中の微細な埃による乱反射を遮断できるため、より鮮明ではっきりとした写真を撮ることができます。
②ハーフNDフィルター
ハーフNDフィルターは、無色透明のガラスとNDのガラスが半々で分かれているフィルターです。
(*NDフィルターとは、ニュートラル・デンシティーフィルターの略で発色に影響を与えることなく、光量のみを少なくするフィルターです)
PLフィルターのようにガラスを枠ごと360度回転させることができ、画面の半分を減光することができます。
【暗い色合いの森とカンカン照りの青空】や【薄暗い道と光り輝くビル群】のような明暗差の激しい風景を撮ろうとすると、暗いほうに合わせたら明るい方が白飛びして明るい方に合わせたら暗い方が黒つぶれしてしまいます。
そこで、このハーフNDフィルターを使って明るい部分にのみ減光をかけることで明暗差が落ち着き、全体的に明るさのバランスを取ることができるようになるという仕組みです。
③クロスフィルター
 クロスフィルターはガラス面に方眼紙のような線が引いてあります。このフィルターを付けて光源を撮影すると、光が屈折して十字の軌跡を写し出してくれます。
クロスフィルターはガラス面に方眼紙のような線が引いてあります。このフィルターを付けて光源を撮影すると、光が屈折して十字の軌跡を写し出してくれます。
イルミネーションや夜の町並みなどをアーティスティックに写し出してくれます。
このフィルターもガラス面が枠ごと360度回転するようになっていますので、光の角度を変えることが可能です。
④センターフォーカスフィルター
 凸レンズの中心部に穴が開いた構造をしているフィルターを、センターフォーカスフィルターといいます。
凸レンズの中心部に穴が開いた構造をしているフィルターを、センターフォーカスフィルターといいます。
穴が開いた中心部を通した部分ははっきりとシャープに写りますが、周囲の凸レンズの部分を通した部分は大きくぼやけたように写ります。この2つの写りが合わさり、独特なボケ写真を撮ることができます。
⑤カラーフィルター カラーフィルターは、色付きガラスを組み込んであるフィルターで、赤・青・黄・緑など様々なカラーがあり、かつそれぞれ色の濃度も数パターン存在します。
カラーフィルターは、色付きガラスを組み込んであるフィルターで、赤・青・黄・緑など様々なカラーがあり、かつそれぞれ色の濃度も数パターン存在します。
このフィルターを付けて撮影すると、写真のカラーバランスや色温度の調整、特定の色味を強調させるなど、意図的に変化させることができます。
⑥クローズアップフィルター レンズの前玉に装着することで簡易的にマクロ撮影が可能なレンズフィルターです。
レンズの前玉に装着することで簡易的にマクロ撮影が可能なレンズフィルターです。
レンズ本来の最短撮影距離よりも近づいて撮影ができます。マクロレンズほどの解像度はないものの、安価で手頃にマクロ撮影を行いたい方にはぴったりのアイテムとなります。
3.作例

④センターフォーカスフィルター

④センターフォーカスフィルター

⑥クローズアップフィルター

⑥クローズアップフィルター

④センターフォーカスフィルター+⑥クローズアップフィルター

③クロスフィルター

②ハーフND+③クロスフィルター

①PLフィルター

①PLフィルター

⑤カラーフィルター

⑤カラーフィルター+④センターフォーカスフィルター
作例をご覧いただきいかがでしょうか。レンズフィルターは重ね掛けで独自の組み合わせを見つけることも出来るのがおもしろい点でもあります!
今回、紹介させていただいたレンズフィルターは、ほんの一部です。
他にも様々なフィルターがありますので、皆様もぜひ色んなフィルターを使ってみてはいかがでしょうか!
*広角レンズで重ね掛けし過ぎてしまうとケラレが出てしまうので注意が必要です。
4.まとめ
デジタルフィルターは確かに便利ですが、どうしても均一的な仕上がりになってしまいがちです。
また、メーカーによっては保存形式がJPEGデータのみしか選択できないため、撮影後の編集で画質を落としてしまう、といったデメリットもあります。
レンズフィルターなら、光の入る角度を工夫したり、効果の強さを自分好みに調整したり、あるいはオリジナルの組み合わせをしてみたりなど、デジタルフィルターでは真似できない様々な効果を出すことが出来るので、表現の幅が広がります!
フォトコンテストなどに応募する際も、デジタルフィルターや過度な現像処理をかけた写真は審査対象外になってしまうことがありますが、レンズフィルターを使用した写真ならレタッチせずとも幻想的な作品で審査対象作品を撮影することができます。そういった意味でもレンズフィルターは良いですよね。
さらにケンコー・トキナー主催の国際フィルターフォトコンテストというレンズフィルターを使用した作品が対象のフォトコンもあるため、コンテスト応募の幅も広がります。
デジタルが進化しつづけている今だからこそ、もう一度アナログな手法を振り返ってみてはいかがでしょうか。
この記事に関するお問い合わせは・・・カメラ担当 米田まで